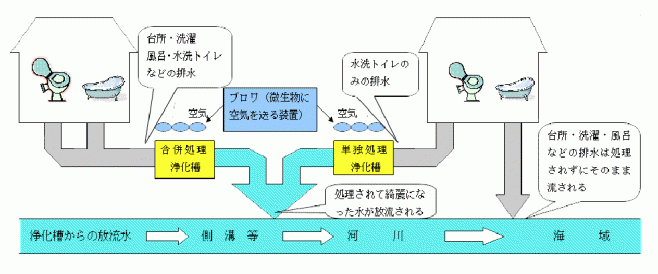浄化槽と上手に付き合うために・・・
浄化槽のしくみ
浄化槽は水中の微生物の働きを利用して、汚水を処理する装置です。微生物がし尿や生活排水の汚れを食べ、きれいな水にしてくれているのです。
浄化槽には、水洗便所の汚水だけを処理する単独処理浄化槽と水洗便所汚水と台所汚水などの生活排水を併せて処理する合併処理浄化槽がありますが、現在単独処理浄化槽の新設は禁止されています。
水洗トイレは使用しているが、下水道に接続されているか、浄化槽が設置されているか分からない方は町担当係にお問い合わせください。また、合併処理浄化槽か単独処理浄化槽が分からない場合は、浄化槽保守点検業者や浄化槽清掃業者にお尋ねください。
浄化槽には、水洗便所の汚水だけを処理する単独処理浄化槽と水洗便所汚水と台所汚水などの生活排水を併せて処理する合併処理浄化槽がありますが、現在単独処理浄化槽の新設は禁止されています。
水洗トイレは使用しているが、下水道に接続されているか、浄化槽が設置されているか分からない方は町担当係にお問い合わせください。また、合併処理浄化槽か単独処理浄化槽が分からない場合は、浄化槽保守点検業者や浄化槽清掃業者にお尋ねください。
浄化槽は使い方と維持管理が大切
トレイを水洗化するために設uした浄化槽も正しい使い方をしないとトラブルが発生します。また微生物が活動しやすい環境を保つ『維持管理』を怠ると、逆に川や海に汚水がそのまま放流され、水域を汚す原因となります。
放流水の水質悪化、悪臭の発生などにより近隣の生活環境を悪くしないよう、適正な維持管理を行い微生物が活発に活躍できる条件を整えましょう。
放流水の水質悪化、悪臭の発生などにより近隣の生活環境を悪くしないよう、適正な維持管理を行い微生物が活発に活躍できる条件を整えましょう。
使用上の注意
トイレ・浴室では
- 洗浄水は、十分な量を流し、詰まり防止のためトイレットペーパ以外の異物(紙おむつ、衛生用品、タバコの吸殻、新聞紙等)は絶対にながさない。
- 掃除には、浄化槽内の微生物に影響するような薬剤(カビ取り剤、漂白剤)の使用は控えめにし、使用後は多めの水で洗い流す。薬用アルコールで消毒とカビの発生を防ぐことができます。
台所・洗濯では
- 台所では、中性洗剤を適量使用し、野菜くずや天ぷら油などは流さない。
- 洗濯は、無リン系やできるだけ中性のものなど塩素系漂白剤を含まない洗剤等をしようする。
浄化槽本体では
- 殺虫剤は使用しない。(微生物に影響します)
- 浄化槽内に空気を送るブロワの電源は絶対に切らない。(微生物が死んでしまいます)
- マンホールのふたはしっかり閉め、上には物を置かず、いつでも点検、清掃ができるようにしておく。
維持管理の3つの義務
保守点検
- 浄化槽機能が正常に移動するためには設備機械、措置の提起点検や補修が必要です。
- 消毒薬の補給(空では放流水は殺菌消毒されません)、消耗品の交換も必要です。
- 浄化槽法に定められた基準及び回数が必要です。(処理方法、規模、用途により異なります。
- 浄化槽保守点検業の登録を受けている業者と委託契約をしてください。
- 保守点検業者から受け取った『記録票』は、3年間保存して下さい。
清掃
- 浄化槽に発注したスカムや汚泥を抜き取り、付属装置や機器類の清掃を行います。
(スカムや汚泥が蓄積されると、浄化槽の機能に支障をきたし、悪臭が発生する原因ともなります) - 年1回以上、浄化槽法に定められた基準により行います。(使用状態により変動します)
- 浄化槽清掃業の許可を受けている業者と委託契約をしてください。
- 清掃業者から受け取った『記録票』は、3年間保存して下さい。
法定検査
- 平常の保守点検、清掃が適正に行われ、浄化槽が正常に機能しているかどうかを確認します。
- 保守点検、清掃業者と委託契約をしていても、その目的が異なりますから、指定検査機関である北海道浄化槽協会による法定検査を受けなければなりません。
- 浄化槽設置後に行う水質検査と、その後毎1回行う定期検査があります。
浄化槽に関する流れ
設置工事契約をする
↓
完成
↓
設置届
↓
法定検査の受検
↓
使用開始届
↓
清掃の委託
保守点検の委託
↓
保守点検等
記録票の保管
↓
完成
↓
設置届
↓
法定検査の受検
↓
使用開始届
↓
清掃の委託
保守点検の委託
↓
保守点検等
記録票の保管
管理者の変更があったとき
- 一般家庭(5、7、10人槽)の時は浄化槽管理者変更届
- ホテルなど事業所関係(500人槽など)の時は技術管理者変更届
を提出してください。